4.撮像素子のサイズとレンズ
図 2-6:撮像素子のサイズ比較
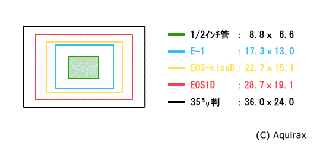 左の図はデジカメのフォーマット、つまり撮像画素サイズを分かりやすくするために、同心円
ならぬ、同心矩形で書いてみたものです。モニター上で原寸表示になっています。
左の図はデジカメのフォーマット、つまり撮像画素サイズを分かりやすくするために、同心円
ならぬ、同心矩形で書いてみたものです。モニター上で原寸表示になっています。
凡例が右に書いてありますが、数字はミリ単位で「幅X高さ」を表しています。
一番外側の黒線がいわゆる 35ミリ判で36X24ミリ、幅と高さの比が3:2で、幅/高さ比率は
1.5になっています。以下小さくなるに従って、赤線:EOS1D が使っているフォーマット、
黄線:EOSkissD や EOS10D などキャノンのCPS サイズ相当のフォーマット(他社にもある
APS-Cフォーマットもこれと近似値)、青線:オリンパス E-1 、緑線:一般的な
1/2インチ撮像管使用のコンパクトデジカメ用と言った順です。
表 2-1:フォーマット比較
使 用 例 幅 X 高さ 幅/高さ 対角線長 対角線長比 面積比 標準レンズ長
A: 1/2インチ管: 8.8 X 6.6 1.33 11.0 3.936 0.07 13mm
B: E-1(4/3#) :17.3 X 13.0 1.33 21.6 2.005 0.26 25mm
C: EOS-kissD :22.7 X 15.1 1.50 27.3 1.587 0.40 32mm
D: Nikon D1X :23.7 X 15.6 1.52 28.4 1.525 0.43 33mm
E: EOS1D :28.7 X 19.1 1.50 34.5 1.255 0.63 40mm
F: 35ミリ判 :36.0 X 24.0 1.50 43.3 1.000 1.00 50mm
いろいろな数字を並べてみましたが、図の中には入れていない、ニコンの D1X のデータも
表には入れてみました。(EOS-kissD と、近似値な為に図ではわかりにくくなるため)
まずは「面積比」を見てください。一般的に広くコンパクトデジカメに使われている 1/2
インチ管の撮像管は、35ミリフルサイズから比べると約 1/14 位の面積しか無いことです。
この中に数百万画素もの素子が詰め込まれている計算ですから緻密さがいかに凄いかおわかり
頂けるでしょう。最近 4/3インチ管として話題をさらっていた、オリンパスの E-1 が約 1/4 と、
やはりコンパクトな撮像管専用新設計のはずなのに筐体が大きいと不評をかっているのも
うなずけます。
次におもしろいのは、35ミリ判以下比較的大きめの撮像管は 1.5 の近似値と同じプロ
ポーションなのに対して、A、Bのコンパクト 2機種のみが、縦横比(幅/高さ)が 1.33 と
スクエアに近いことで、おもしろい傾向です。もともと撮像管はビデオカメラ用として開発
されたもので、管と言うからには丸いチューブ状の形状から発達しているので、効率を考えると
同じサイズの円に外接する矩形の場合は正方形が一番面積が大きくとれることに関係があるの
でしょうか?。
ここからが次の話しに繋がるのですが、対角線長と対角線長比が、最も注目すべき点です。
「対角線長比」とは、便宜的に(35ミリ判の対角線長/撮像管の対角線長)を表し、
よくカタログなどに表示される35ミリ換算○○ミリという計算の係数になるものです。
つまり E-1 の場合、レンズの表示焦点距離を 2.0 倍した数字が 35ミリ換算値を表し。
同様に kissD なら表示値の 1.6 倍が換算値ということになります。表の中で最小の
1/2インチ管の場合は、ほぼ 4倍の換算になるというわけです。
そして、一番右に記された「標準レンズ焦点距離」ですが、良く耳にする、「コンパクト
デジカメは、ちゃんと写りはするけど、背景が上手くボケずに狙ったものが背景の中に埋没して
しまう」理由がおわかり頂けるのではないでしょうか? つまり、カタログにはたいてい35ミリ
換算値のみが大きく表示されていて、(実際の焦点距離は小さく諸元表に書かれるのみ)関心を
持たれませんが、13mmという被写界深度の深いレンズなのです。つまりぼかすのが難しい
レンズでいかにしてぼかすかなどというのは、ばかげたことですよね。思い切った方法を使わ
ないと好ましい結果を得るのは大変に難しいということです。
ところで35ミリ換算とはどういうことを表すのでしょうか?
換算とは、つまり35ミリ判における標準レンズの画角(対角線画角:46゚)を基準にして、
それぞれの撮像管サイズで対角線画角 46゚ のレンズを標準レンズと見なしていると言う
ことです。
つまり画角上は 46゚ と標準レンズ相当の画角ですが、焦点距離が短いため、レンズ固有の
深い被写界深度などは付いて廻るのです。ピントの精度が多少甘くても何とかなると、メーカー
は考えているわけでも無いでしょうが、デジカメ撮像素子の値段がデジカメ本体価格を左右して
いると言っても言い過ぎでないほど大きなコスト要素らしいので、小さくて汎用性が高い撮像
素子のほうが、メリットが大きいのでしょう。
ぼけにくいレンズを使用したカメラで小物を撮影する場合、できるだけ絞り値を開けて少し
でも被写界深度を浅くする工夫をこなし、尚かつ被写体と背景の距離がなるべく確保できる
アングルとそういう被写体を捜すことが、まず最初に必要なアプローチと心しておいた方が良い
でしょう。
▼APS-Cフォーマット
APSサイズで3種から選べるフォーマット中最小のサイズでC(クラシック)30.2X16.7mmの
大きさの画面のこと。
デジカメの場合、当初ニコンのD-1発売の際に、素子サイズ(23.7X15.6mm)を「APS-Cサイズ
にも匹敵する」と、誇大(?)な広告で広めたためにそう呼ばれるようになったが、逆に言えば
撮像素子のコストがカメラの金額を決めてしまうほど高価なパーツなため、35ミリフルサイズは
欲しいが、撮像素子周辺部へ入る角度が付いた光線では、極端に感度が落ちてしまうという
特性もあり、一回り小さなこのサイズが、レンズ交換式一眼レフデジカメの主流の座へ付いた。
現在発売されている 10数機種の前記デジカメ中のほとんどが、このサイズで占められて
いる。
▼APSフォーマット
新規格として一世を風靡したかに見えたフォーマットです。
アドバンスト・フォト・システムの略で、35ミリ判のフィルムに取って代わろうと、主に
フィルムメーカーが作り出した規格です。そもそも35ミリ判とは、フィルム幅が35ミリの
シネフィルム、つまり映画用のフィルムを使ってドイツのライカが編み出したフォーマットで
ライカ判とも呼ばれます。我が国でも、ニコンで一時期横幅を詰めた 32X24mmサイズのカメラを
出していたが、混乱が生じることから、今のサイズへと統合されたいきさつがある。
一方肝いりでスタートしたAPSですが、かつてとは格段のフィルム性能上昇に、
一般使用ではオーバークォリティ過ぎると判断した結果、7割ほどと細身の24ミリ幅に、
撮影途中いつでも画面サイズを横幅の違いから3種から選べたり、パトローネフィルムの
メリットをより勧めてカメラ装着の簡便さ、撮影途中でもフィルム交換が可能なように
フィルムを外に出すと先端部はカートリッジ内部に収納されたり、カメラの中では自動的に
引き出されて、撮影可能状態になるなど最新の技術を集結して企画されは、したのですが
いかんせん時期も悪かったようです。ユーザー側への配慮に欠けた、撮影後のネガはパトローネ
のままで保管を余儀なくされたり、現像後画像確認も直にネガではできないために、必ず
インデックスプリントと称するべた焼きを作らねばならず、整理の煩わしさ、そして
コスト的にも値崩れし尽くした35ミリフィルムに対抗するには、あまりに開きすぎた大きな差を
埋めるには至らず、自然消滅気味に…
そして追い打ちを掛けるように台頭してきたのが、本題のデジカメです。
ところがマイナス面だけでは、ありませんでした。APS規格に則ったカメラを各メーカー
しのぎを削って開発した成果は、現在のデジカメの基礎へと形を替えはしたものの、生かされて
これほどまでに短期間で花開いた原動力となったと言えるはずです。
▼べた焼き(……やき=コンタクトプリント)
今でこそ、親切なネガフィルム撮影の現像を出すと、現像代だけでサービスサイズプリントが
無料で付いてくるなど、当たり前な時代になりましたが、昔はフィルム現像と同時にモノクロの
べた焼きプリントを注文したものでした。ネガフィルムの場合は、先の「デジカメの構造」の
項でも少し触れたように、元の色の補色で組み上げた画像として残されていますので、いくら
目が肥えたと言っても、人間の目には補色から逆算して元の色を想像するのは至難の業で、
ピントの確認や構図のチェックなど、必ずこのべた焼きで研究してプリントしたもの
でした。
ラッシュプリントともインデックスプリントとも呼ぶようです。
![]()
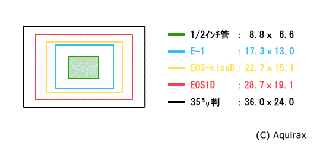 左の図はデジカメのフォーマット、つまり撮像画素サイズを分かりやすくするために、同心円
ならぬ、同心矩形で書いてみたものです。モニター上で原寸表示になっています。
左の図はデジカメのフォーマット、つまり撮像画素サイズを分かりやすくするために、同心円
ならぬ、同心矩形で書いてみたものです。モニター上で原寸表示になっています。